
成富 研二氏
琉球大学 名誉教授
沖縄南部療育医療センター 嘱託医師(遺伝医学)
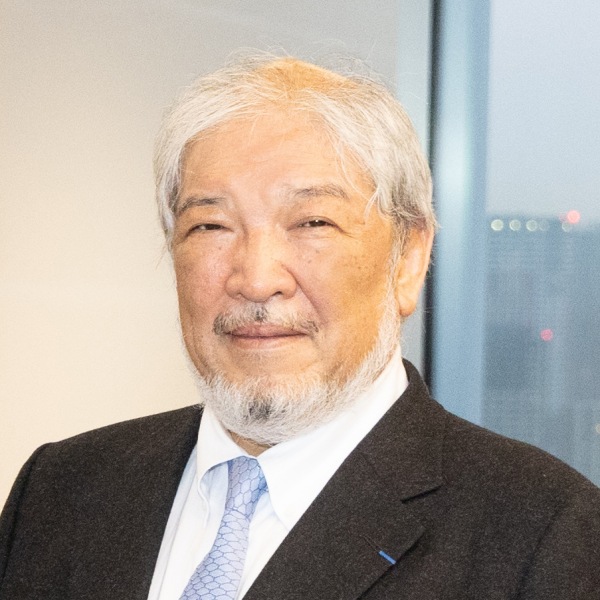
松田 文彦氏
京都大学 総長主席学事補佐
京都大学大学院医学研究科
附属ゲノム医学センター センター長・教授

先崎 心智
日本アイ・ビー・エム株式会社
IBMコンサルティング事業本部
ヘルスケア&ライフサイエンス・サービス
パートナー/理事
難病とは、厚生労働省によると「治療が難しく、慢性の経過※をたどる疾病」とされている。日本では、医療支援を受けることができる「指定難病」に指定されている疾患群が338(2024年3月現在)あるが、この338疾患群に含まれる難病の数は数千に及ぶ。日本だけでなく世界的にみても、各難病の患者数は少ない半面、難病数は多いという傾向があり、どの地域や集団でも人口の6〜8%が難病患者と推察される。中には病名がわからないまま苦しんでいる人もおり、専門医の診察を早急に受けられる仕組みづくりが長年の課題である。
AIを活用した難病情報照会アプリケーションである、患者や家族といった一般向けの「Rare Disease-Finder(以下、RD-Finder)」と、医師や研究者向けの「Rare Disease-Finder Pro(以下、RD-Finder Pro)(IBM外のWebサイトへ)」は、難病患者と専門医を結びつけたいという思いから誕生した。RD-Finderは、自然言語を使って難病情報を検索することができるという特徴がある。RD-Finder Proは、診断や研究の助けとなる情報を導き出す。
この難病情報照会AIプロジェクトの発端となった、同アプリケーションが活用する遺伝性疾患の総合データベース「UR-DBMS」を構築した、琉球大学 名誉教授であり、沖縄南部療育医療センター 嘱託医師の成富研二氏と、京都大学大学院 医学研究科 教授であり、同研究科附属ゲノム医学センター長の松田文彦氏を招いて、2016年よりこのプロジェクトに関わり続けている日本アイ・ビー・エム(以下、日本IBM)の先崎心智が、難病医療に対するお二人の想い、難病医療の現状、難病情報照会AIの狙いなどを伺った。
※ 慢性の経過:症状が急激に悪化することはないが、緩やかに症状が進行したり、治らずに停滞したりしている状態。
「君みたいな人が役に立つこともある」と言われて遺伝子研究の世界へ

先崎 最初に、先生方がどのようなキャリアを経て難病の研究に携わることになったのか教えてください。
松田 私は高校まで数学が得意だったので、京都大学 理学部に入学して数学を学びました。ところが、同学部には、数学ができる人は掃いて捨てるほどいましてね。卒業したら数学はやめてほかの道に進もうと思っていた頃、友人に誘われて大阪大学の医学部医科学修士課程を受験したら合格。ただ、数学出身は即戦力にならないので、どこの研究室でも断られてしまった。最後にたどり着いたのが、当時、すでに分子生物学では日本のトップだった本庶佑先生※の研究室でした。先生は「君のような人材がそのうち役に立つこともあるだろう」と僕を拾ってくれました。
こうして分子生物学者として遺伝子研究の道を進むことになって、本庶先生には15年ぐらい指導していただきました。そのあとフランスに渡り、新設されたフランス国立ジェノタイピングセンターという研究所に就職しました。今でこそ「ゲノムワイド関連解析(GWAS/病気と遺伝子の関連性を網羅的に解析する手法)」は認知を得ていますが、当時は革新的な研究で、研究所はその草分け的な存在でしたね。
フランスで驚いたのが、将来役に立つかもしれないと収集してきた膨大な遺伝性疾患の家系記録と生体試料があったこと。フランスは植民地を持っていた経緯から、北アフリカや中東とのつながりが強い。それらの地域はもともと部族社会で「いとこ婚」が多いため、遺伝性疾患も多い。そんな背景から、研究機関に属していない小児科医などであっても、患者の家系図などを記録したり検体を採取したりしてきたようです。
※ 京都大学特別教授。2018年にノーベル医学生理学賞を受賞。
先崎 日本には同様の記録があまりなかったのでしょうか。
松田 はい、当時日本では遺伝性疾患はタブーとして扱われていましたから。フランスにいた10年間で多くの遺伝性疾患の研究に取り組むことができました。その中には、遺伝性が強い「先天性全身性脂肪萎縮症」などもあります。そして、研究を進めるうちに、難病はゲノム医学の専門家が取り組むべき分野だと理解しました。帰国してからは、難病のゲノム解析やオミックス解析を研究の大きな柱の1つにしています。
先崎 もう1つの大きな柱が、京都大学が滋賀県長浜市と一緒に進めている「ながはま0次予防コホート(IBM外のWebサイトへ)」事業ですね。
松田 はい。長浜市に住む1万人の健常者を長期にわたって観察し、継続的に収集した血液や尿、環境・生活習慣情報を用いて、ゲノム・環境と病気の発症や老化の関連を解析するものです。難病研究において、患者の集団と比較する対照群として用いることができます。これらが難病研究を進めるにあたって重要な2本の柱で、この2本柱があるから研究が進められています。
先崎 フランスで10年間研究活動をされた際、日本との違いを感じましたか?
松田 私がいた部署は、ほかの研究者と頻繁にやり取りがあったわけではないので、多くない付き合いの中から感じたことになりますが、フランスではコンセプトをしっかりつくってから作業に入ることが多いですね。
例えば、データベースを構築するデータサイエンティスト(バイオインフォマティシャン)は、コンセプトを固めてから構築を始めます。逆に言えば、コンセプトがあやふやならやらない。十分に時間をかけて構想を練り、きちんとしたスキーマ(定義)を書き、それに合わせてデータベースをつくっていくのです。フランスでは、子どもの頃から哲学的な「思考のプロセス」を学ぶので、その影響があるのでしょうね。
先崎 そのスタンスは、研究スタイルにも反映されているのでしょうか。
松田 そうですね。例えば免疫学を考えると、一つひとつの細胞が何をしているのか、一つひとつの分子の役割は何かがわかっても、免疫は大きなネットワークなので、全体を制御するバックボーンはどこにあるのかを突き詰めていくことが大切です。そこに、より的確に切り込むことができるのが、コンセプトをしっかりつくってから研究を進めるフランスのやり方だと思います。
先崎 ちなみに、本庶先生がノーベル賞を受賞された時、松田先生はフランスにいらっしゃったのですか?
松田 受賞がアナウンスされた時は京都におり、ノーベル財団のライブ動画を見ていました。お名前が出た時は自分のことのように嬉しかった。ストックホルムで開かれた授賞式には、私も行きましたよ。
診断システムを自分で構築、情熱の源は2年間の療養生活
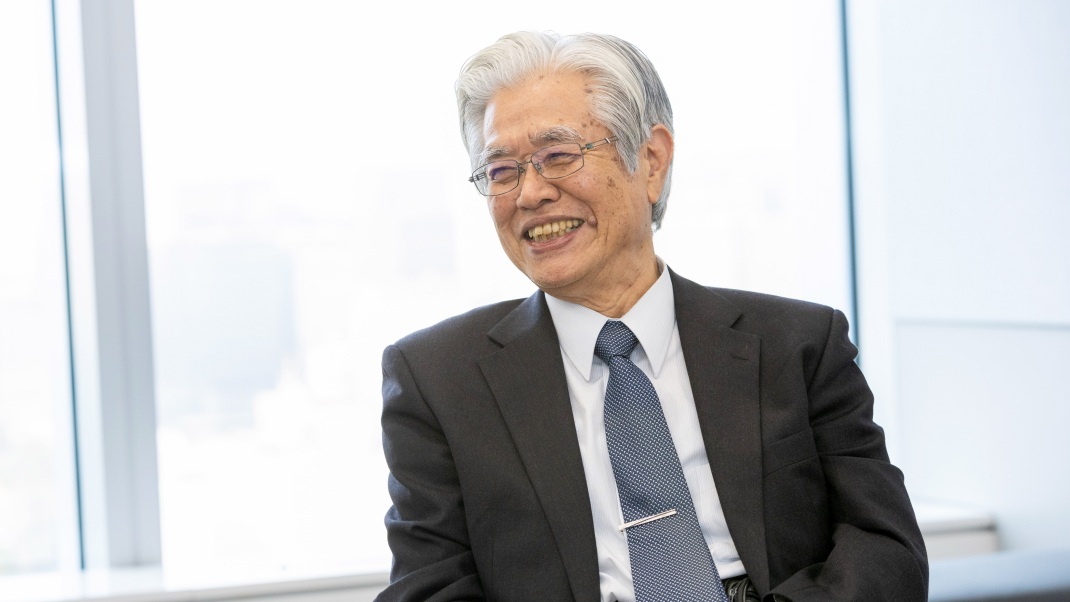
先崎 成冨先生はどのようなキャリアを経て難病の研究に携わるようになったのでしょうか?
成富 僕は佐賀県出身で、鹿児島大学医学部に進みました。大学時代に遊んでばかりいたツケが回ってきたのでしょうか、医師国家試験が終わり研修医採用時の健康診断で肺結核と診断され、そのまま療養所生活になりました。一番元気よく働くことができる時期の2年間、療養生活をしていたわけです。療養生活中は、小児科を志望していたことから、小児科の教科書『ネルソン小児科学』を原書で3回読んで全部ノートに訳しました。ノートを積み重ねると数十センチの高さになりましたよ。
無事に退院して大学の医局に戻って、「さて何を専攻しようか?」と。入院時に親切にしてくれた先生が遺伝の研究をされていたので、そちらに進むことに決めて遺伝医学の世界に入りました。
やっと一人前になったかなという時期に、指導医の先輩が琉球大学の助教授に転任されることになりました。だから僕は、医者として現場に立って3年で鹿児島大学の遺伝グループの班長になりました。どうにかこうにか、周囲の助けを借りながら研究に取り組んで、少しは研究費がいただけるようにもなりました。
先崎 その後、琉球大学に赴任されたのでしょうか。
成富 もともと英国に留学したいと思っていたので、京都にあるブリティッシュ・カウンシルで試験を受けて。1回目は予想どおりダメでしたが、「来年また応募してください。可能性がありますよ」とカウンシルの英国人に勧められていました。ただ、そのタイミングで所属していた鹿児島大学の寺脇教授に「(助教授として)沖縄に行きなさい」と命令されたのです。
僕は当時35歳、この年齢で医学部の助教授になれるというのも運命だろうと思って沖縄行きを決めました。こうして、花のロンドン留学が沖縄行きに変わってしまったわけです。その頃は染色体の分析方法が急速に進化している時期でした。高精度分析ができるようになって、新しいことがどんどんわかってくる。1年間で7〜8点の英文論文を出すことができました。
先崎 那覇に行かれ、遺伝医学の研究者としてより成長されたのですね。
成富 助教授になったからできたことでしょうね。時を同じくして「遺伝性疾患診断のためのPCシステム」づくりにも取り組みました。外来には遺伝性の奇形症候群の患者さんが来られるのですが、なかなか診断がつかない。そうなると、この分野の第一人者である、山口大学の梶井正先生、神奈川県立こども医療センターの黒木良和先生、北海道大学の新川詔夫先生に診断を仰ぎます※。ただ、診断基準については「見ただけでわかる」と返されてしまう。でも僕らは、“見ただけ”ではわからないのですよ。
そこで、コンピューターを使って症状を組み合わせて診断できるシステムをつくれないかと考えました。ちょうどその頃、英国や豪州では同様のシステムがつくられつつあって、そこで使われているコンピューターは日本製だったから、ならば自分でできると思ったのです。調べたところ、一番適していると判断したのがNECとIBMのコンピューターでした。わずかの差でIBMの性能が良かったので「IBM-5400」にしました。当時で130万円ぐらい。MS-DOSの頃で、車を買える値段でしたね。
教授に「買ってくれないなら鹿児島に帰る」くらいの勢いで直訴してIBMのコンピューターを買ってもらいました。最初に染色体高精度分染分析用のシステムをつくり、偶然かもしれないけれど、最初の患者さんの診断がうまくいった。「これはいいぞ」ということになって、奇形症候群まで収録範囲を広げることにしました。
※ 3名とも所属は当時のもの。
先崎 今回の難病情報照会AIプロジェクトは、私たち日本IBMが支援させていただいています。数十年前にもご縁があったことは、とても嬉しく思います。ご自分でシステムをつくられるにあたって、苦労されたことはありますか?
成富 もちろんありましたよ。当時のコンピューターですから、1つのフィールドに入力できる文字数が256字で、症状を入力するとオーバーフローするわけです。考えた末、症状を入力する代わりにコード化することにしました。だから、HPO※のオリジナルをやり出したのは僕なのです。
また、UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)で学生がMacを自作しているのを見かけてね。そのMacを使って図も描いている。これはいいなと、今度はMacを買って、さっそくフィールドの文字数制限が少ないソフトを使ってデータ入力を始めました。最初は症状のデータのみを入力していましたが、症状に関連する遺伝子が分かるようになってきたので遺伝子関連の情報の入力も始めました。
それまでは症状と診断でしたが、データが蓄積されてくると症状と遺伝子の一致も見ることができます。原因となる遺伝子を調べる研究領域も活発になりました。病名にも、タイプ1・タイプ2といったように原因遺伝子による番号が付与されるようになって、診断のためのデータをどんどん増やしていくことになりました。
※ 「Human Phenotype Ontology」の略。ヒト疾患における表現型を記述する統制語彙・オントロジー。未診断の臨床症状の相互比較や登録を行うことができる。
先崎 小児科でスタートして遺伝医学の道に進み、コンピューターを使ったシステムを自ら構築された。医学とは違うスキルが求められることも成し遂げています。ものすごい実績だと思います。
成富 そう言っていただけると嬉しいですが、単に新しいもの好きなのですよ。




