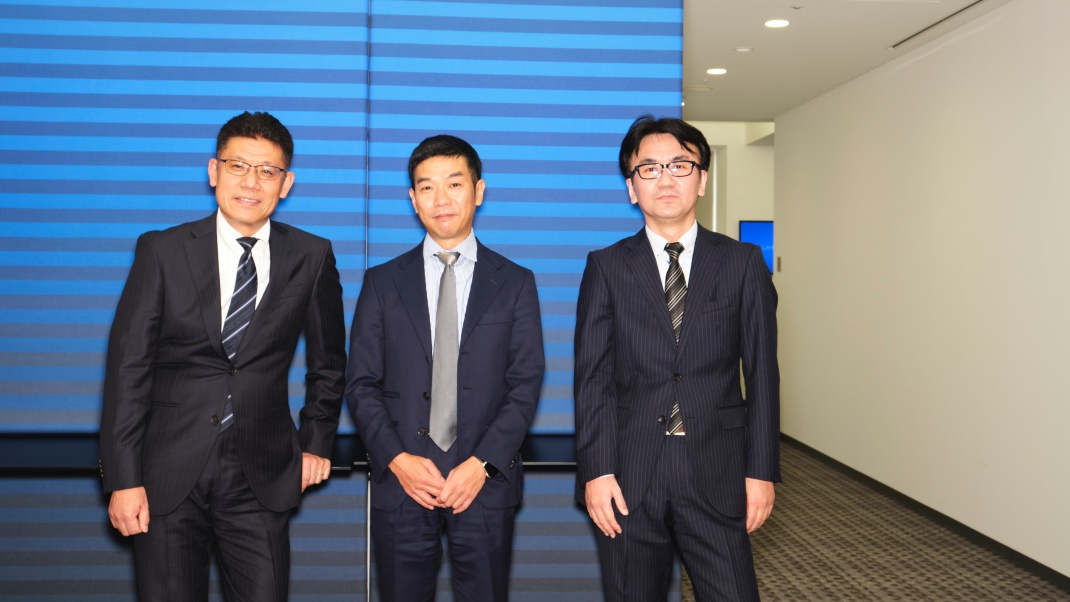人文社会科学系の学問と情報理工系の先端技術を融合し、社会課題を起点に従来にはなかった概念や社会モデルをデザインする、東京大学と日本アイ・ビー・エム(以下、IBM)の協同プログラム「Cognitive Designing Excellence(以下、CDE)」。2019年7月から始まり3年間の予定で行われているが、2年目となる2020年度最後の研究会が、2月3日にオンラインで開催された。
2020年度は1年を通してアーティストとともに社会課題に向き合ってきた。今回の第1部のゲストスピーカーは水族表現家の二木あい氏。講演後は、2月に福島県浪江町で新しいモビリティのあり方について考える「スマートモビリティチャレンジ」に携わっている日産自動車株式会社 常務執行役員 アライアンスグローバルVP 総合研究所所長の土井三浩氏を中心に、人と人が出会えるための街づくりについて議論を行った。
水中で生きる生物と人間の架け橋となるために表現活動を行う

第1部は水族表現家の二木あい氏による講演。二木氏は1980年に石川県で生まれ、3歳から水泳を始めた。自らが撮影者や被写体となり、水中での写真や映像を通して水族の営みを伝えている。「水族表現家」というのは二木氏の造語で、「水の中を人間目線ではなく、水に生きる部族の一員として伝えたい」という思いから名乗っている。潜るときはスキューバダイビングではなく必ず素潜り。スキューバダイビングのほうが長く水中にいられるが、息をするときに音と泡が出てしまう。それでは水族の中に一員として入ることはできないため、あえて素潜りにしているそうだ。
2011年には、メキシコにある水中洞窟セノーテで、「洞窟の中を一息で一番長く泳ぐ」種目において2つのギネス記録取得に成功した。1つはフィンあり100m(1分52秒)で女性初。フィンなし90m(2分2秒)は男女関わらず世界初。これに挑戦した理由は「エゴを追求するためではなく、自分のメッセージを世界へ伝えるために発言権を得たいから」と明かす。地球の70%は海であり、海がなければ生物は呼吸もできないし、食物もできない。海は日常から切り離された別の世界ではなく、私たちと深くつながっているということを、「架け橋となって、伝えていきたい」と語る。
地球で共に生きるため、言葉を越えて通じ合えることを伝える

二木氏は魚の群れに入って泳ぐ。13頭のザトウクジラと一緒に泳いだこともある。サメやシャチなどにも恐れることなく接近する。巨大なサメに正面から向き合った写真は衝撃的だ。
「『怖い』という思いは、水中でバイブレーションとなり、陸上の4倍早く伝わってしまう。つまり、自分が『怖い』と理解する前に相手に伝わってしまうのだ。いくら怖がったところで、自然で私たちはなす術はなく、考えて行動では遅い世界。だからこそ、過去や未来ではなく、今ここにいることに集中する。反発するのではなく、その流れに乗る。何事も全て必ずサインがあるので、それを見逃さないように感覚を研ぎ澄ませておくことが重要。考えは横に置いておく」(二木氏)
さらに、相手を尊重しコミュニケーションすることも大切だと言う。
「テクノロジーが進化し、人間はいろいろな形でコミュニケーションを取ることができるが、自然の中でクジラの親子と間近で出会うと、生き物として本来持っている愛のかたちを突きつけられる感じがする。私たちがどこかに置いてきてしまった、本当に大事なものを、彼らを通して伝えていきたい。忘れてはいけないのは水中は彼らのお家であるということ。土足で入るのではなく、彼らをリスペクトし、正直に向き合うことで初めてコミュニケーションが取れる」(二木氏)
自身が撮影した写真展では、クラゲとそれによく似たプラスチック袋のモノクロ写真を並べて展示したが、海洋ゴミだとは前面には出さなかった。問題提起するうえで先に「どれだけ人間が悪いか」突きつけてしまうと、本題に入る前に目を背けられてしまうと考えるからだ。「この美しいものは何?」と見る人に想像してもらうことで、スルっと心に入り、事実を知った時に他人ごとではなく、自分ごととして受け取ってもらうことが目的だからだ。「理解をしてもらうというより、心に直接語りかける」「理解しても、心がYES!とならないと本当の意味で何も変わらない」と思うからだという。
「テーマは“共に生きる”。私たち人間は地球の所有者ではありません。水中・陸上関わらず全てが共に地球に生きるものであり、その一員として人間は何ができるか。母なる海から種の枠・言葉の枠を超えたつながりを表現することで、心の深い部分に伝わるはずだと信じて活動しています」(二木氏)
街を活性化させるために、モビリティを通じて人の出会いを創出

二木氏の講演後、フィッシュボール形式で議論が行われた。フィッシュボール形式とは、何人かがインナーサークルとして中心に出て議論を進め、その周りに観察者がいる。観察者も意見がある場合は随時インナーサークルに入り、議論する人と観察する人が柔軟に入れ替わる形式を言う。
今回、インナーサークルには二木氏と、議論のテーマを提案した日産自動車株式会社 常務執行役員 アライアンスグローバルVP 総合研究所所長の土井三浩氏、その他に、日産自動車 総合研究所モビリティA&I研究所所長 山村智弘氏、鹿島建設株式会社 副社長執行役員 海外事業本部長 越島啓介氏、パナソニック株式会社 イノベーション戦略室室長 下田平麻志氏、東京電力ホールディングス株式会社 常務執行役 関知道氏、東京大学大学院情報学環 学際情報学府教授 Ph.D. 中尾彰宏氏、東京大学大学院工学系研究科 准教授 小渕祐介氏が参加した。(ファシリテーターは日本IBM 柴田順子)
議論のテーマは2つ。
1 「群というもの(まちにヒトが集まり、ヒトとヒトが出会うということ。群としてのクルマ、群としてのサカナ。まち、群にとって適正なサイズとは)」
2 「使命感がドライブする仕事(使命感を持つヒトが集まるコミュニティのチカラ) 」
テーマを提案した土井氏は、福島県浪江町で経済産業省、国土交通省、さまざまな企業や自治体と共に考えるプロジェクト「スマートモビリティチャレンジ」に携わっている。東日本大震災の前に浪江町には約2万人の住民がいたが、福島第一原子力発電所の事故のため全員が避難生活を余儀なくされた。現在は一部の地域を除き避難指示が解除され、約1500人が戻ってきて復興を目指している。プロジェクトは、人口が少なくなった浪江町で持続可能な新しいモビリティを模索し実証実験を行う取り組みだ。
土井氏は、「『MaaS』(モビリティ・アズ・ア・サービス=手段を問わずに移動を一つのサービスとして提供する)という動きがあるが、単に人を動かすだけでは足りない。街をもう一度活性化させるためには地元のコミュニティが大切だ」と語る。
「車は、“速く便利に安全に快適に”を追求してきたが、車は周りを見渡すことはできない。移動の途中はデザインしていないと言われたことがある。人がなんのために移動するかなど、車にはいろいろ見直すこと、考えることがあるのではないか。移動する目的を作らないと、人と人は出会わない。それがないと結局は街に貢献できないのではないか。移動をデザインすることは自動車会社だけではできない。さまざまな方と相談しながら、どうやって街を作り、出会いはどうあるべきか、移動はどうあるべきか、未来における移動のイメージを考える。外から来た人間だけでなく、中の人たちが一緒になって作っていく。その活力をどうやって作っていくか」(土井氏)
テクノロジーを使い、効率化だけで測れない“つながり”を生む

議論では街づくりについてさまざまな意見が交わされた。関氏は街に必要なものについて次のように語った。
「人と人が集まるためには生命を維持するためのインフラとしていろいろなものが必要。昔、馬車を使っていた頃に都市の人口が何で決まっていたかというと、馬の干し草や人間の食料である小麦の収穫量だった。生物に必要な基礎的なものがある程度あったうえで、さらに知的生物である人間として必要なものがある。このバランスが大事。浪江町のプロジェクトでは、生活基盤というインフラの整備と、産業の育成は絶対に行わなければならない。そのうえで、浪江町に住むことの意味や意義を積み上げていかなければならないように思う」(関氏)
パナソニックは神奈川県藤沢市、横浜市、大阪府吹田市で「サスティナブル・スマートタウン」というプロジェクトに取り組んでいる。住宅やウェルネス複合施設などを有する先進的なスマートシティを構築する一方で、技術を使って醤油を借りるようなご近所付き合いを現代にふさわしい形で復活させる「SOY LINK(ソイリンク)」という関係作りにも力点が置かれている。
「ソイリンクは、今は失われてしまった日本の温かい近所付き合いが醸成できないか、リアルスペースとしての情報発信基地を組み合わせながらトライしています。その際、いろいろなスキルやモノの相互利用やマッチング、あるいは情報の伝達や拡散をテクノロジーで実現しようと考えています。コミュニケーションが活発化すれば、その街に住み続ける価値につながるのではないか」(下田平氏)
小渕氏は、電気も水道もない砂漠で年に1度で開催される「バーニングマン」という米国のイベントについて語った。バーニングマンは、コミュニティー、芸術、自己表現、自立を重んじる。参加者はテントやキャンピングカーで街を作り、約1週間にわたって共同生活を営み、アートや音楽やダンスや交流を楽しむ。お金を使うことはいっさいできず、参加者はなんでもいいので自分が何かを与えることでバーニングマンへ貢献することを求められる。お金をベースにした資本主義ではなく、完全な自由の中で各人がお互いに与え合うことで、共同生活を成立させている。年々参加者が増え、今や世界中から7万人以上が集まる巨大イベントだ。
「私が参加したのは30年ほど前で、今ほどの規模ではありませんでした。バーニングマンは、ユートピアンシティという理想的な都市を描いた短期間のイベント。全員が何かしらの形でコミュニケーションを取り、モノの売買はしないけれども交換したりシェアしたりする。誰もが参加できる社会はどういうものなのか。インクルーシブについて根本的に考えさせられる街。今求められているような効率や利便性はないけれど、心をつなぐことを追求するのがバーニングマンではないかと思います」(小渕氏)
議論を観察していた参加者からは浪江町について「避難していた住民のうち1500人が戻られたのは、シビックプライド(市民としての誇り)のような何かがあったのでしょうか」という質問が寄せられた。
土井氏は「シビックプライドがあったかどうかはわかりませんが、『どういう街にしたいですか』と聞いたところ、『これから育つ子どもたちがプライドを持てる街にしたい』とおっしゃっていた住民の方がいました。浪江町はこれからどういう拠点になっていけるか、どういうアイデアが生まれ日本の地方に向けて発信できるか。そこに私も貢献していきたいと思っています」と回答した。
中尾氏は先端技術を研究する立場から、技術を生かした街づくりに必要なものは「効率化だけではない」と語った。
「みなさんの話を聞いていて、技術は手段に過ぎないと痛感しました。技術者は、“効率化”が最終のゴールだと考えがちなのかもしれない。我々は最新の情報通信を使って自動運転を実証実験しています。「移動」ということだけを目的にすると、それで効率の良い移動が達成できます。しかし、大学で自動運転の講義をしたときに、ある学生からこんな意見を聞きました。『自動運転は素晴らしい技術ですが、私はドライブを楽しみたい。だから機械に運転してほしくない』。そのときハッとしました。我々は、別の実証実験で5Gによる遠隔監視というデジタル革命(DX)の活動を進めています。たとえば海中は危険だから水中ドローンを遠隔操作して可視化するというマインドです。しかし、二木さんのように自ら素潜りをする方もいらっしゃる。技術ですべてを効率化するのではなく、あらゆる人のことを考える、つまり多様性や包摂性の視点が重要なのではないか。これがスマートシティの新しいポイントなのではないか。技術はツール。効率化だけでなく、地元の方の思いやプライドを守り、地域の経済や文化の継続性を担保するという方向に使うことも必要ではないか」(中尾氏)
社会課題の解決に向け、社会モデルのデザインに注力した2020年度

1時間以上にわたる示唆に富んだ議論の後、年度末の総括があった。まず、日本アイ・ビー・エム株式会社 専務執行役員 グローバル・ビジネス・サービス事業本部長 加藤洋氏は、来期への期待を寄せた。
「コロナウイルスの感染拡大を防止するためにニューノーマル時代のやり方としてリモートに変更しましたが、総合的には良かったと見ています。参加いただいた方がオンサイトだと50人くらいでしたが、リモートにしてから100人を超えています。CDEをどういう目的で始めたか振り返ってみますと、先進デジタル技術と人文社会科学を融合して新しい社会モデルを作ることです。ポストコロナ、ウィズコロナの世界では特に必要な議論であり、この1年を通して多くのディスカッションを行い、新しい社会モデルの創出に一歩一歩近づいてきています。4月からは3年目に入ります。これからもみなさんとCDEから社会に対して発信し、アウトカムを出して貢献していきたいと考えています」(加藤氏)
続いて中尾氏と、東京大学名誉教授 中央大学国際情報学部教授 東京大学大学院情報学環境 特任教授 須藤修氏も、それぞれ次のように語った。
「今日のディスカッションを聞いていて、議論の盛り上がりは中身やコンテンツによるものであって、バーチャルかどうかはあまり関係ないと感じました。年度末最後にふさわしい、充実した内容の会だったと思いました」(中尾氏)
「このプロジェクトの最初に読んでいただきたい本として、ハンナ・アーレントの『人間の条件』を紹介しました。アーレントは、人間の基本的要素は『労働』『仕事』『活動』と書いています。『労働』とは苦役とトラブル、『仕事』は主体性があってやりがいのあること、『活動』は社会や全体性を見ながら新たなビジョンを指し示していく人間として重要なもの。アップルの研究者を経てベンチャーキャピタルのCEOを務めている李開復(リ・カイフ)は、『AIは苦役から人間を解放してくれる。新たに人間の仕事と活動の領域をどう編成し直すかが重要だ』と言っています。私もUNESCOのAIの倫理に関するハイレベル会合で、『AIを怖がってばかりではいけない。苦役から解放してくれる可能性が高い。同時に我々は教育や研修を徹底し、新たな能力を身につけて仕事や活動という人間として重要な領域で能力を発揮できるようにしなければならない』とプレゼンしました。これは私自身の意見でもあるし、李開復の意見でもあります。各国代表の約1200人から拍手が起こって共感できるのだと思いました。その点について我々でもう少し肉付けしていければ」(須藤氏)
最後は、二木氏の力強い言葉で締めくくられた。
「私たちは人間であって機械ではないので、自動運転など機械ができることは機械に任せて、自分たちじゃないとできないことをすることが大事。自己満足のプライドではなく、突き動かされる使命感がないと、私たちの未来である子どもたちに伝わらないと思う。今さえよければいい、自分さえよければいいという時代は終わった。未来に向けて地球で共に生きる、相手を考えたコミュニケーションが大事」(二木氏)
アンコンシャスバイアスを破壊し、社会課題の認識・理解を行った2019年。社会課題を解決するために、社会モデルのデザインに注力した2020年。2年間の活動を経て、最終年度となる2021年度は、いよいよ社会モデルの実現方法について考える。
この記事に関連するサービス
研究プログラム「Cognitive Designing Excellence」では、東京大学が持つ人文社会科学系や先端科学系の卓越した知見と、IBMが持つAI、ブロックチェーン、IoT、量子コンピューターなどの先端デジタル技術を融合し、日本企業の強みを生かしながら持続的成長を実現する社会モデルの創出を産学連携で推進します。