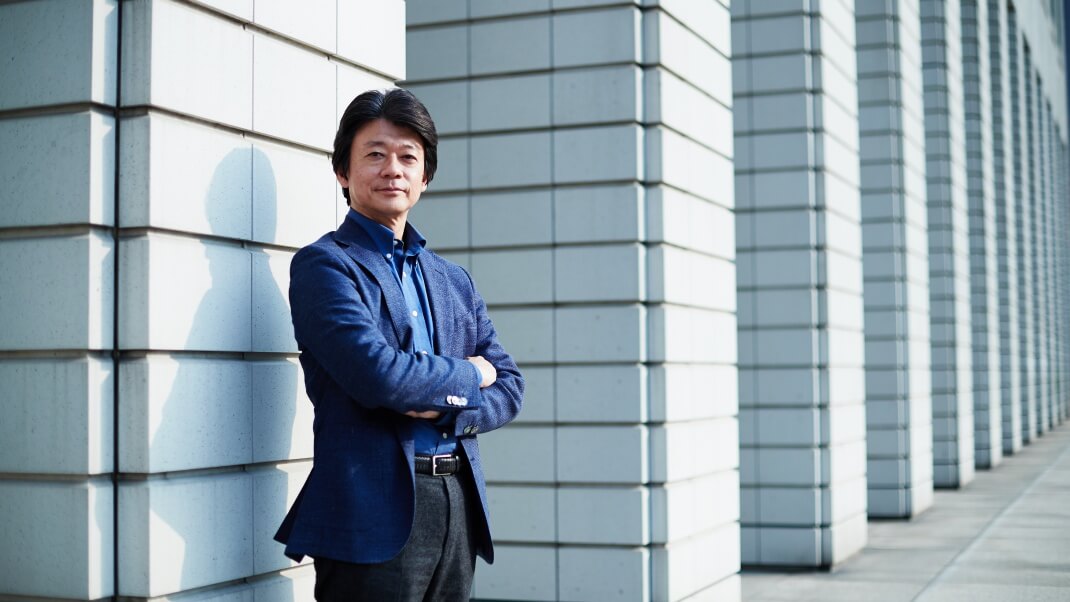課題解決やイノベーションの実現のため、さまざまな企業の新規事業プロジェクトやアイデア創出イベントなどで活用される「デザイン思考」。その思考法を企業経営に活かしたものを特に「デザイン経営」と呼ぶが、日本全体の産業競争力強化のため、政府も本腰を入れて取り組み始めている。2018年5月には特許庁が「『デザイン経営』宣言」を発表した。
その動きの中で、グローバルな競争力の源泉である知的財産(知財)を取り巻く状況の変化に対応するべく生まれたのが「デザイン経営プロジェクト」だ。約1年が過ぎた現在、プロジェクトの成果と進捗はどのようになっているのか。
特許庁「デザイン経営プロジェクト」プロジェクトチーム長の今村亘氏、同チームスタッフで意匠審査官の外山雅暁氏と、株式会社インフォバーン代表取締役CVO(Chief Visionary Officer)小林弘人氏が、デザイン経営が描き出す変革とビジョンについて語った。
![]()
今村 亘
特許庁 審査第二部 運輸 審査長
デザイン経営プロジェクトチーム長
1994年特許庁入庁。機械分野の特許審査・審判、米国留学等を経て、2014年から2017年まで知財アタッシェとして日本貿易振興機構(JETRO)ニューヨーク事務所に勤務。2018年7月に新たに立ち上げたスタートアップ支援チームを率い、特許庁のスタートアップ支援施策の指揮を執る。現在、「デザイン経営プロジェクト」においてプロジェクトチーム長を務める。
![]()
外山 雅暁
特許庁 デザイン経営プロジェクト 総括チーム
2001年特許庁入庁。意匠審査官、国際課等を経て、2012年から経済産業省デザイン政策室でデザイン政策を担当。デザイン思考推進のための研究会を実施。2018年2月から特許庁デザイン経営プロジェクト立ち上げのため、庁内の調整や研修を行い、2018年8月のプロジェクト発足からは総括チーム及び広報チームに所属。現在はデザイン経営の普及プロジェクトも並行して行う。
![]()
小林弘人
インフォバーン 代表取締役Chief Visionary Officer
1994年「WIRED」日本語版を創刊し、1998年に株式会社インフォバーンを設立。ブログメディア「GIZMODO」日本版を立ち上げる。2016年に独・ベルリン市主催のAPW2016でスピーカー、同じくベルリンのテック・カンファレンスTOAの公式日本パートナーも務める。現在はインフォバーンにてブロックチェーン・ビジネス・ハブ「Unchained」の主宰としても活動。
ブランド構築とイノベーションをもたらす「デザイン」

小林 特許庁の「『デザイン経営』宣言」では、「デザイン経営」を「デザインを企業価値向上のための重要な経営資源として活用する経営である」と定義し、自ら「デザイン経営プロジェクト」を立ち上げられました。そもそもなぜ「デザイン経営」に着目されたのか、経緯からお聞かせ願えませんか。
今村 まずデザインというと、特許庁にはそれに関連する法律として「意匠法」があります。意匠法はいわゆるデザインの知的財産を保護するための法律ですが、今の法律ができた当時と比べると保護する対象がずいぶん変わってきており、時代の変化に合わせて見直しを行う必要が出てきました。そこで特許庁では、2017年7月から経済産業省と共同でデザインの政策と意匠法の今後を話し合う「産業競争力とデザインを考える研究会」という検討会を立ち上げました。だいたい月に一回のペースで実施し、2018年5月までの全11回の中でまとまった話を報告書にしたものが『「デザイン経営」宣言』だったんです。
私たちが庁内で推進している「デザイン経営プロジェクト」も、その中で策定されたデザインの定義をベースにしています。
小林 最初は意匠法改正の検討会から始まったものだったのですね。「産業競争力とデザインを考える研究会」にはどんな方々が集まり、どんなことを話し合われたのでしょうか。
今村 デザインに関してさまざまな角度から意見が出ることを目的として、研究会にはデザイナーはもちろん、経営コンサルタントや学識関係者などの方々を委員としてお招きしました。多様なメンバーでスタートした研究会でしたが、まずいきなり知って驚いたのが、お恥ずかしいことですがデザインというものは我々が思っているようなプロダクトデザインだけではない、ということでした。研究会では、意匠法改正の議論の前に、そもそもデザインとは何かという話が始まりました。
外山 もともと意匠法というのは「物の形」を保護する法律でした。そのため、特許庁の人間にとって「デザイン」とは、プロダクトデザインを指すものでした。しかし、この研究会を通して、デザインに対する新たな定義を持つ必要があることに気付かされました。
ただ一口に定義と言っても、人によってデザインの捉え方はバラバラです。なかなか綺麗な形にまとまらず、「デザインの定義」についての議論が半年ほど続きました。それがある日「ブランド」と「イノベーション」でデザインを定義できるのではないか、というところで皆が腑に落ち、最終的に「デザイン経営」という考え方に収束していきました。
小林 デザインは単に「物の形」としての意匠だけではなく、特にブランドを構築する、目に見えない要素の重要性を認識されたわけですね。

今村 そうです。デザインには「ブランド構築に資するデザイン」と「イノベーションに資するデザイン」の2つがあると、我々は考えました。前者においてのデザインとは「企業が大切にしている価値、それを実現しようとする意志を表現する営み」であり、それがメッセージとして伝わることでブランド価値が生まれていきます。後者においてのデザインとは「人々が気づかない潜在ニーズを掘り起こすもの」であり、そのニーズに対応するサービスの事業化を構想することでイノベーションが生まれていきます。このように、改めてデザインの定義づけがなされたわけですが、もちろん、慣れていない人間にはすぐに理解できるものではありません。我々も何度も集まって考えを共有していくうちに、各々が自分なりに腹落ちさせていったというのが正直なところです。
若手の変化で効果を実感。デザイン経営実践に向けて全庁的に取り組みを開始
小林 そうしてできあがった「デザイン経営」の概念を、自ら実践してみようということで立ち上げられたのが「デザイン経営プロジェクト」ということですね。
今村 おっしゃる通りです。加えてプロジェクトの発足には、当時、特許庁長官だった宗像直子氏の存在が大きかったと思います。宗像自身が研究会に参加しながら、「まず自分たちでやってみよう!」という考えを持つようになり、2018年8月に、庁内にデザインを統括する責任者としてデザイン統括責任者:CDO(Chief Design Officer)というポストを作りました。そして、CDOの下に「UIチーム」「海外チーム」「国内スタートアップチーム」「国内中小・ものづくりチーム」「国内サービス・ブランディングチーム」「広報チーム」というテーマの異なる6つのプロジェクトチームが発足したのです。
小林 プロジェクトメンバーは庁内からの公募で集められたと聞いています。
今村 チーム発足に先立つ8月に、部署やキャリアの域を超えた60名のメンバーが集まりました。もっとも、「『デザイン経営』宣言」を出す前の段階でしたが、長官の呼びかけで若手の職員を対象としてデザイン経営をテーマに研修を行ってはいたのです。しかし研修を実施しただけで、それを報告書として提出して大丈夫だろうかという思いが長官にはあったと思います。
そこで一度、研修に参加した若手職員たちに内容を踏まえた課題を与えて報告させたところ、普段は上司や先輩の後ろで座っているだけの彼らがいきいきとプレゼンを始めたんですね。これには長官もデザイン経営の考え方を導入した成果を肌で実感されたようです。最終的には、「自分たちだけが研修を受けたのでは不足している。上司や先輩も受けるべきだ」という若手の声を取り入れ、管理職や特許庁の幹部、長官自身も研修を受けることになりました。「デザイン経営」について、ある程度の知識を若手からトップまでが共有したところでプロジェクトがスタートしたという順序になります。
ユーザー目線を徹底することで見えてきた、本質的なニーズとやるべきこと
小林 「デザイン経営プロジェクト」の前段階にあたる「『デザイン経営』宣言」では、「デザイン責任者(CDO、CCO、CXOなど)の経営チームへの参画」や「デザイン経営の推進組織の設置」などを、デザインを経営に落とし込むための具体的取り組みとして挙げていますが、それらをさっそく実行に移されたということですね。6つのプロジェクトチームはそれぞれどんな活動をされたのでしょう。

今村 チームごとに課題とユーザーを設定し、カスタマージャーニーマップの作成からスタートしました。それから、洗い出された課題についてユーザーインタビューを行い、最終的には合宿をしながらメンバー全員でソリューションを創出していきました。
広報チームを例に挙げると、将来の産業を支えるこどもたちの知財意識や技術への関心を高めることを目標に、毎年夏休みの時期に開催している「こども霞が関見学デー」というイベントの再検討を始めました。
ところが、こどもたちへのインタビューを通じて見えてきたのは、これまでの「こどもたちの知財意識を高める」という目標は、実はユーザーであるこどもたちが求めているものではなく、供給者視点での目標であったということでした。そこで、ユーザー視点に立って、目標を「こどもたちに創造性の本質を伝える」に転換しました。この目標をこどもたちにも伝わるよう、「きみの手で“あたらしいワクワク”をつくろう!!」と言い換え、科学技術が好きなこどもたちが創造をしたくなるような仕掛けを盛り込んだ実地テストを行い、その成果をイベントの全体設計やコンテンツ作成に活かしました。
外山 私もチームのメンバーとしてイベントに参加しましたが、今年度は、「こども霞が関見学デー」に加えて、科学技術が好きなこどもたちの集まる国立科学博物館でも初めて開催しました。具体的には、身近にある製品をヒントに発明品を考えるワークショップを実施し、そのこどもたちのアイデア創出によりイベント内通貨「トッキョマネー」を得られる仕組みを導入しました。こどもたちからは楽しい経験になったとの感想が聞かれ、好評を博しました。
特許庁の仕事というと、大多数の方は「出願を受け付けて審査する」という部分だけをイメージすると思います。実は我々もある意味では同じでした。それが今回のプロジェクトでカスタマージャーニーマップを作成したことで、ユーザーが何かしらの発明をしたとして、どうやって出願するのか、登録されたあとはどうやって使うのか、ユーザーの疑問を時系列に沿って網羅的に把握することができました。デザイン経営という視点を持つことで、これまでの自分たちがいかにユーザー目線でなく特許庁の業務の中だけで仕事をしてきたか、に気づくことができました。

今村 スタートアップチームの場合、いろいろな起業家の人にインタビューをしてみると「知財ってなに?」というところから話が始まるんですね。その後、「自分たちは虎の子の技術を持っているけれど、それで特許を取れるなんて知らなかった。じゃあ、取るにはどうすればいいのか。専門家がいるのか。いるとして、どうやったらつながることができるのか」といった話になることがすごく多かったのです。そこで、弁理士さんとのマッチングができるサイトの開設や、通常14ヶ月かかる審査期間を1ヶ月まで短縮することができる「スーパー早期審査」という仕組みの構築に取り掛かりました。実はこのスーパー早期審査はすでに始まっていて、現時点で200件の特許出願が対象になっています。
またUIチームでは、「特許庁のオフィスアクションをもっとわかりやすくユーザーに伝える」ということミッションに設定しました。出願の中には1回では審査を通らないものもあります。その際、特許庁では出願人に「拒絶理由通知」というものを出しています。内容的には「この部分がこういう理由で特許にはならないので直してください」というお知らせなのですが、「拒絶」の二文字だけで諦めてしまう人が多いんです。正規の法律用語ではあるのだけれど、これをUIやUXとして考えるとちょっと言葉が強すぎる。そこで、通知にQRコードを付けて、スマホで読み取るとすぐに対処方法がわかるサイトに飛ぶようなアイデアが出ました。
加えて海外チームでは、近ごろ海外企業の日本での出願が減少傾向にある原因について検証してみました。出願数の減少は、マーケットとしての日本の魅力の低下が原因と予想していたのですが、実際にヒアリングしてみるとそればかりではありませんでした。日本で特許出願をするには日本語への翻訳が必要なのですが、どうやらこの翻訳作業が壁となっているらしいとわかったのです。
外山 出願する側としては、まだ審査を通過するかわからないものをすべて翻訳するには費用がかかりすぎる。こうした気付きを得ると、そこからまた新しいアイデアが生まれます。これはすごく良い循環だと感じました。

【写真:左】可動式のテーブル
自由にレイアウトを変更できる可動式のテーブルを設置。プロジェクト用に新調するのではなく、簡易なボックスを活用。中には今までのアイデアの試作品が入る。
【写真:右】メンバーが自由に使えるツール類
ペンや付箋など、アイデア出しに必要な道具が揃う。壁掛けにして整理することで誰でも使いやすく、意見を可視化しやすい環境を整えた。
デザイン的思考がもたらす組織の変化とグローバルで戦うための武器
小林 プロジェクトチームの活動を通して、職員のみなさんが考えるデザインの定義がどんどん拡張してき、ユーザー中心主義のサービスを自ら提起されたことと察します。それによって組織的にはどんな変化があったでしょうか。
外山 さすがに約2800名いる職員全体に「デザイン経営」が浸透したとは言えませんが、プロジェクトに参加した60名を中心に、研修を受けた400名は考えを共有できていると感じています。
「『デザイン経営』宣言」では具体的な取り組みの一つとして「アジャイル型開発プロセスの実施」を掲げていて、プロジェクトの各チームも実践しました。我々公務員は、課題に対して直線的に解決策を探すという考え方をしがちですが、プロジェクト内の取り組みでは考えをどんどん拡散してアイデアを膨らませていくことを意識しました。

小林 特許庁が実践した「デザイン経営」は当然民間企業にも当てはまるものですね。すでにグローバルではデザイン思考は当たり前で、次には、もう一度価値を問い直す「意味のイノベーション」(*注1)が提起されていたりします。そこにたどり着く前にも、日本企業の多くがデザイン経営に取り組むためには、何が大切だと思われますか。
外山 日本にはすでに独自にデザイン経営を実践している企業がいくつかあります。今年は特許庁が主催している知財功労賞のカテゴリーに「デザイン経営」を加え、デザイン経営を実践している企業として無印良品の良品計画やアウトドアメーカーのスノーピークを表彰しました。デザイン経営を実践している企業に共通しているのは、社内で目標と意識の共有ができていることだと思います。若手だけでなくトップや管理職がどれだけ本腰を入れて変化に取り組めるか。この辺りがグローバルで戦う際の最初のポイントになってくると考えています。
今村 いいアイデアを生み出すには失敗を許容することも大切だと思います。まずはやってみて、失敗したら次は違うアプローチでトライする。アジャイル型開発で、観察、仮説構築、試作、再仮説構築を反復して、スピーディーに良いものを生み出してける組織になる必要があります。そしてそれを許容して応援していく環境や社会が整うことで、企業や行政が新しいものを生みだし、グローバルな競争力を持つことができるようなります。今回のプロジェクトでも、「とりあえずやってみよう」とスタートして、「やっぱり違う」と別のアイデアに乗り換えるチームもあったのですが、最終的に「駄目だった」と言った参加者はいませんでした。方向転換したことで全然違うアイデアが生まれていくのを間近で見ていて、この動きをもう少し日本社会に広げていけたらいいと感じました。
2025年を区切りに示したい、特許庁による「デザイン経営」のビジョン
小林 IoTとAIの普及で進むと言われる第4次産業革命で、知財の在り方も変化していくと思われます。確かに保護も必要ですが、イノベーションの創出には、知財の活用がより重要になってくると予測します。たとえば、オープンイノベーションによって若いスタートアップ企業が無償で知財を使用できたり、死蔵している企業の知財を売買できたり、そういったことを可能にしていく必要があると思います。

今村 おっしゃる通り知財の活用は非常に重要で、今まさに着手しているところです。知財のなかには企業が自社の利益を守るためだけに保有していたり、使われなくなってしまったりしたものが数多くあります。いたずらに売却するといわゆるパテント・トロール(*注2)などに渡ってしまう可能性もあるので、その点に注意しつつ、眠った知財をいかに流動化させるかがポイントとなります。
同時に、意匠法の改正によって守るべき権利をしっかりと守れるようにしていきたい。従来の意匠法ではいわゆる物と一体になったデザインでないと登録できませんでしたが、これまで権利保護できなかった、たとえばUIなどでも、優れたものは意匠権として登録できるようにしていければと考えました。物品と一体となっていないようなデザイン、たとえば、クラウド上に存在するデザインでも登録可能にするといったように、時代の変化に合わせたものに改正しました。
小林 さまざまな分野で時代の変化への対応が必要になってきますね。特許庁として、「デザイン経営」を今後はどういう方向に進めていきますか。たとえば、特許庁がバックキャスティング(*注3)を用いて考えた「特許の未来」とか、そのロードマップを見てみたい気がします。ぜひ、お願いいたしますね(笑)。

今村 現在、一つの目標としているのが2025年の「大阪・関西万博」です。これに向けたプロジェクトチームを今年7月に発足させました。万博は夢を語る場だと思っていますので、これからの6年間で、我々なりの知財の将来像について夢を交えながら議論していくつもりです。その成果をなんらかの形にして万博で展示することで、一つの結びにしようと考えています。
*注1:意味のイノベーション
イタリア ミラノ工科大学教授 ロベルト・ベルガンティ氏(Roberto Verganti)が提唱する考え方。
「デザイン思考」が、既に判明している課題を解決するためのソリューションを探求するプロセスであるのに対し、「意味のイノベーション」とは、解決するべき課題の設定を考察の対象とすることであるとされる。
*注2:パテント・トロール
自らが保有する特許権を侵害している疑いのある者(主にハイテク大企業)に、該当の特許権を行使して巨額の賠償金やライセンス料を得ることを狙う者。多くの場合、その者自身はその特許に基づく製品の製造販売やサービスの提供などは行っていない。
*注3:バックキャスティング
未来を予測する際、物事を考える起点を未来に置いて、そこから現在を振り返って今何をするべきか考えること。従来の考え方では答えの出ない問題(地球規模での持続可能な社会の実現、温暖化の防止など)を考える上で用いられることが多い。
現在の諸要因から、実現可能性の高い未来を予測する現在起点の考え方(フォアキャスティング)と比較して語られる。