私たちが生きる現代社会は、実は劇作家シェイクスピア(1564-1616)や哲学者ジョン・ロック(1632-1704)が生きた近世イングランドと驚くほど似ている-そう主張する歴史家がいる。イングランド経済史・経営史を研究する東京大学・山本浩司氏だ。その主張を支えるのが、山本氏が今年6月に上梓した一冊の本『Taming Capitalism before its Triumph』(オックスフォード大学出版局)だ。山本氏によると、当時のイギリスでは新規事業(project)が社会に大きなしわ寄せを生み出した場合には、さまざまな人々のvisible hands(見える手)が介入し、社会に禍根を残さない、より持続的な事業モデルが模索されていた。
デジタルシフトが進む今、AIやブロックチェーンなどのテクノロジーによって非連続的な革新が起きている。日本社会とそこに息づく企業はこの波を、どのように乗りこなすべきか。山本氏と日本IBMでコンサルタントとして活動する岡村周実の対話から、テクノロジー企業による「新規事業」や「技術革新」のあり方を考えていきたい。

山本浩司
東京大学 経済学研究科 経営史・近世英国史 講師
ビジネスによる社会問題の解決可能性と、その際の困難について歴史的に考察する。12年強のイギリス滞在(ケンブリッジ大学研究員等)を経て、2016年4月から現職。TEDxスピーカー。

岡村周実
日本アイ・ビー・エム グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略コンサルティング アソシエイト・パートナー
さまざまな業界でパブリックセクターとプライベートセクターをつなぎ、両者の課題解決や新たなエコシステム創生を主眼に活動を続ける。
近世イギリスでは「錬金術」のメタファーでビジネスが語られていた
岡村 山本先生が執筆された『Taming Capitalism before its Triumph』を拝読しました。先生の研究分野はイングランド経済史・経営史ですが、この本では近世イギリスにおける「企業の社会的責任」の前史にスポットが当てられています。
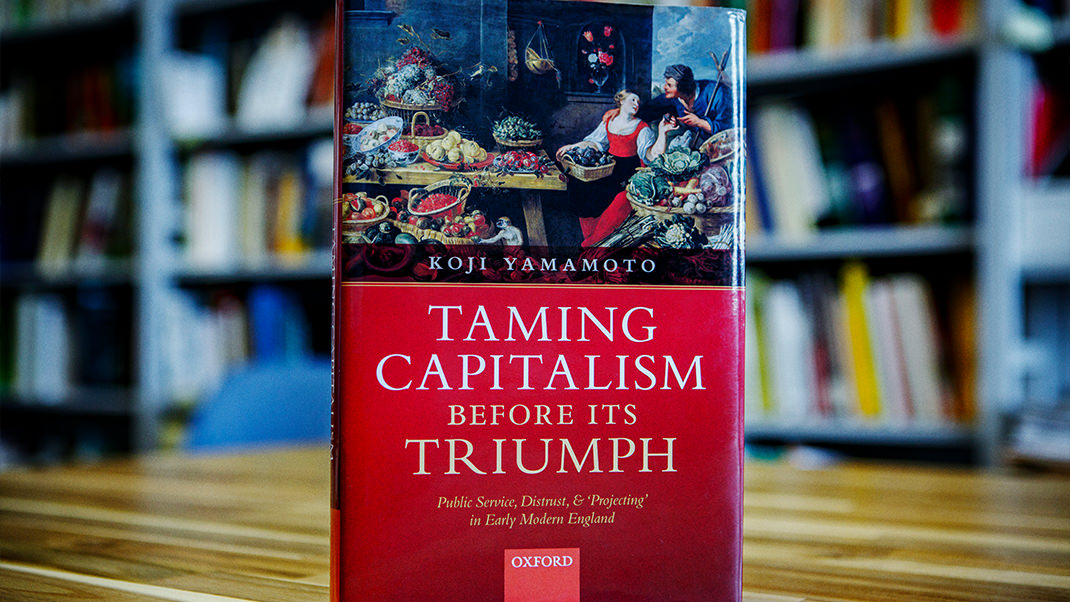
読んでいて特に印象深いと感じたのは、「project」という言葉が多用される時代があったという部分です。大航海時代を経て産業革命の時代へと向かいつつあった近世イギリスは、『業を企てる』――すなわち企業という活動体が生まれた時代にあり、そこでは今で言う新規事業や技術革新のような活動、つまりprojectが多く生まれていたと書かれています。
山本 現在でも、世の中には政府だけでは解決できない社会的な問題が存在しますよね。それは、近世イギリスでも同じことでした。そこで中世以降、特に16世紀の中頃までには爆発的にヨーロッパ各地でビジネスによる問題解決が図られるようになります。すなわち、大学の外にある知識やノウハウを社会という共同体の問題解決に役立てる活動がプロジェクト事業として数多く立ち上がった。
岡村 それらは、今の民間企業のDNAとも言い換えられそうです。projectという言葉の内容自体は、現在と大きく変わらないのでしょうか?
山本 当時の文人や技師たちはnature(自然)よりもart(人為/技芸)のほうが優れている、と主張していました。人間の技芸をもってすれば、自然や社会が抱えている問題をよりよい方向に変えていけると考えていたのです。ルネサンスが華ひらいた時代です。経済の領域でも、人間の可能性を信じ、最大限活かそうという風潮が生まれつつあった。projectは、その「人為への信頼」を代表するような概念でした。
岡村 一方で project を“being associated with unscrupulous schemes for getting money”——お金を獲得するための、本当は詐欺まがいの事業 と捉える人もいたそうですね。
山本 当時の人たちも、やはり人間の人為(art)が社会を無条件に幸せにするのか疑問を抱いていました。そんな留保を象徴したのが「錬金術」です。錬金術は迷信のようなものではなく、ニュートン(1643-1727)ら科学者が熱心に取り組んだ、現代風にいえば「R&D」の一部でした。その錬金術で、鉛や銅を金・銀に変える「賢者の石」を作り出す工程の一部を、当時の人々はprojectionと言ったのです。

私の研究では、そうした「錬金術」のメタファーで、当時、ビジネスが語られていたことが明らかになりました。金銀の生成に失敗した錬金術師が詐欺、ペテン、大言壮語……などと言われてしまうように、ビジネスで社会問題を解決しようという取り組みにもまた、ネガティブなニュアンスが多分に含まれていました。「本当にうまくいけば、すごい」「でも本当にできるのだろうか」と、当時のビジネス事業は、錬金術をパラダイム(ある時代のものの見方、考え方を支配する認識の枠組み)として理解されたのでした。
社会不信(distrust)といかに対峙するべきか
岡村 良いprojectもあれば、悪いprojectもある。ただ、当時の人々がprojectorと呼んだ起業家たちがいないと社会は良くならない——。今という時代を考えるうえでも示唆に富んだお話だと思いました。さらにもう一歩踏み込んだトピックとして、山本先生に伺いたいことがあります。それが、テクノロジーのこれからです。
最近、ブロックチェーン技術をベースとした暗号通貨による市場の混乱がありました。また、AI技術による無人自動兵器の開発プロジェクトに対して、世界中のAI研究者がボイコットを表明するといった報道もありました。更に、今年5月に適用・施行されたGDPR(EU一般データ保護規則)は、「市民が自らのパーソナルデータの保護・移動をコントロールする権利」を、市民自身が取り戻す・・という動きですが、施行の背景には、これまでそれを奪っていた“Digital Giant”への不信があったのは明白です。
デジタル技術を扱うprojectだけでなく、最近では高度プロフェッショナル制度やシェアリングエコノミーなど、政策系・社会経済系projectも進められていますが、こうした現代の諸事業も、やはり「どのような結果をもたらすのかわからない」と、市民から不信の目を向けられているような感覚が私にはあります。

そこで注目を集めているのが、テクノロジーの「運用」です。我々IBMのような企業が常に対峙しなければならないのは、進化するテクノロジーの用途・運用を信用しきれない、すなわち「それがもたらす結末が、どうなるのかわからない」という、人々のdistrust(不信)です。
近世イギリス社会では、市民からのdistrustにどう対峙してきたのでしょうか。
山本 人々の不信とは、常にネガティブなものとは限らず、むしろリテラシーとも重なる積極的意義がありました。不信は文化だったとすら言えそうです。なかでも、メディアの力がとても大きかった。メディアといっても新聞だけではなく、例えばシェイクスピアやベン・ジョンソン(1572-1637)が創作する舞台劇なども大きな役割を果たしていました。
岡村 具体的には、どんな役割があったのでしょうか?
山本 当時イギリス市民の識字率はとても低かったのですが、下町にある劇場に行けば、シェイクスピアら劇作家の劇を観ることができました。そして、作中では政治のことやprojectのことなど、時勢について語られていた。そこで膨らませた「想像力」の駆動がビジネス・リテラシーの向上に一役買ったことが分かりました。
岡村 現実世界のさまざまな新規事業を戯曲のプロットのなかに混ぜ込み、舞台というメディアで表現し、その戯曲について市民が議論することで、社会全体で不要な不信を避け、一方で信頼できる事業と社会に害悪を及ぼす事業を見分ける方法を探っていたのですね。
山本 こんな話もあります。産業革命の最中、18世紀にイギリスで出版された『ガリヴァー旅行記』では、著者であるジョナサン・スウィフト(1667-1745)が当時の新規事業を風刺しています。作中に登場するある島にはprojector(起業家)のアカデミーがあって、そこではクモの糸から布地を作ったり、人の堆肥から食物を作ったりしている。スウィフトはそんなprojectorたちを、物語のなかで揶揄しているんです。
さらに、この話には続きがあります。結果的に『旅行記』は大ヒット。イギリスの多くの家庭で愛読されました。そうして再版も決まるのですが、スウィフトは新たに書きなおした序文のなかで「この本の出版もまたprojectである」と公言した。
つまり「これは、社会をよくするため、文学という作品に値段をつけて世に送り出したproject」であり、さらには「この本を出しても社会は良くならない。もうこりごりだ」と皮肉ったのです。
岡村 なるほど(笑)。非常に面白いお話です。メディアによる想像力の駆動も、万能ではなかった訳ですね。
時代をコントロールするのは“visible hands”(見える手)
岡村 ところで、先ほどGDPRの話をさせていただきましたが、中国では市民のパーソナルデータを監視して、市民個々人を社会信用スコアで格付けをする「新たな信用経済・社会システム」のような動きも起こっていますよね。これもある種の壮大な実験と考えられますが、projectorはこうした経済・社会システムの創造にも関わってきたのでしょうか?
山本 はい。イギリスでも市民戦争(ピューリタン革命)期(1642-1651)には、急進的な宗教活動家たちが、神の意図にしたがった完璧な社会システムの構築をトップダウンで実現しようと試みたことがありました。ただし、細かいところまでデザインし尽くされた社会システムは、それがどれだけ善意に基づいていても限界があるようです。そして、そうした試行錯誤の歴史のなかで生み出されたのが、自由競争市場を前提とした資本主義なんだと思います。
岡村 なるほど。資本主義といえば“Invisible Hand”(見えざる手)という言葉があります。アダム・スミスの『国富論』のなかにある言葉で、経済の議論では「個々の市場参加者が自らの効用のみを最大化すれば、市場全体を見ても、効率的な資源配分と経済成長の達成が自然と均衡する」といった意味で使われ、「神の見えざる手」と訳されることもあります。
デザインされ尽くされた社会に重大な問題があるとしたら、私たちはどう考えれば良いのでしょうか。市場はやはり「見えざる手」に任せるべきなのでしょうか? 先生は本のなかで、当時の変わりゆく経済状況のなかでは、人々による不断の介入があった・・と記されていて、そこではスミスを意識した “visible hands”(見える手)という表現を使っておられます。

山本 アルフレッド・チャンドラーという経営史研究者は『The Visible Hand』という本を1977年に発表しています。彼はこの大著のなかで、需給の関係によって自然と最適解が決まっていくマクロな視点だけでなく、もっとミクロな、経営者の「見える手」によるマネジメントが果たした役割の重要性を説いています。それを理解しないと19世紀以降の産業の発展はわからない、と。私の論点は「経営者以外の多様な『見える手』も重要だったのではないだろうか」というものです。
岡村 市場メカニズムや資本主義システムといった規範自体もinvisible handだけでなく、法規制や業界ガイドライン、品質基準といった「見える手」による産物ですよね。
山本 これからの時代を考えるうえでも、私は経営者だけでなく、消費者やメディアを含めた様々な「見える手」の介入があってしかるべきだと思いますし、テクノロジーの文脈でも企業にはその気づきを期待しています。テクノロジーが進化し、人々の期待や熱狂に任せておけば、自動的に社会が最適化されるわけでは決してない。テクノロジーを人々がどう使いこなし、何を不信の対象と定めるのか、うまくいかない可能性があることを含め、その時々の対処が必要です。
岡村 まったくその通りだと思います。
山本 もう1つ言えるのは、今の時代にテクノロジーの議論をする場合、エコロジカルな限界に人々がどう向き合うのかが重要視される、ということです。これまで続くと思われてきたものが続かなくなる可能性もある。テクノロジーだけで、エネルギー等のあらゆる社会問題を解決できると思っていたら、それこそ不信の対象となった 「錬金術師」と同じことになってしまいますから。テクノロジーの可能性は計り知れませんが、万能ではありません。「テクノロジーが奉仕すべき正しい目的とは何なのか」。この問題を社会全体で討議し(『ガリヴァー旅行記』や舞台作品のように)楽しく学べる仕組みとリテラシーの醸成も重要でしょう。ビジネスチャンスは、そこにもあるかもしれません。
岡村 多くの技術革新が矢継ぎ早に生まれるデジタルシフトの時代において、これから企業がすべきことは、破壊的なテクノロジーをさまざまなユースケース——すなわち一種の「戯曲」として表現しつつ、自らと自らを取り巻く「社会の見える手」によって数多のdistrustをも止揚していく道筋を探りながら、projectを着実に生態系の中で前進させる…ということなのかもしれません。本日はどうもありがとうございました。
東京大学経済学研究科 山本浩司・ホームページ 山本浩司『Taming Capitalism before its Triumph』 Twitter: @koji_hist




