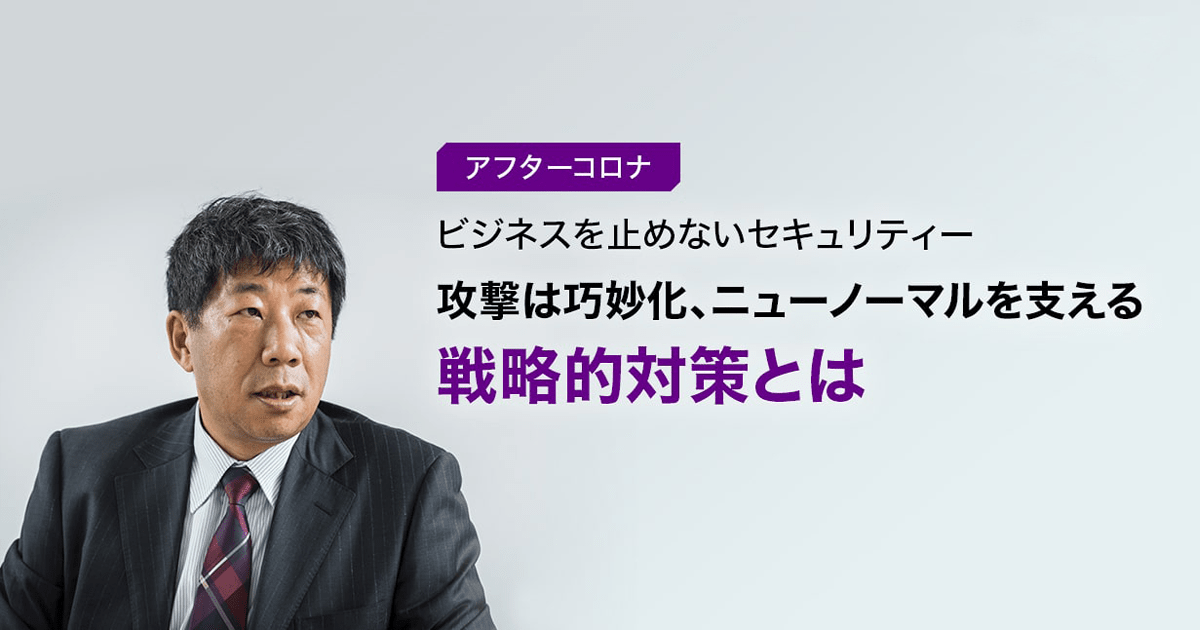とあるオフィスを想像してください。そのオフィスは、社員一人あたりの空間が通常のオフィスよりも数倍広く確保されています。静かで、日当たりがよく、ソファや音響設備も揃っていて、快適に過ごせる配慮がされています。キッチンもあるのでいつでも食事が取れますし、コーヒーだって飲み放題。夜にはアルコールも供され、終日リラックスしながら集中して仕事に取り組めそうです。都心のオフィス街からは離れた場所にあるため、満員電車で疲弊することもありません。保育園からも近いので、子供と過ごす時間を少し増やすことができそうです。
但し、一つだけ条件があります。オフィスは1週間のうち2日しか利用できません。
こんなオフィス、いかがでしょうか。最後の不思議な条件さえなければ…と思いませんか? でも、皆さんはこのオフィスを新規契約する必要はありません。なぜなら、すでに「自宅」という形で保持しているからです。
仲田清人
エンタープライズ・アプリケーションズ事業部 アカウント・プロモーション
日本IBMにて、基幹業務/システムの標準化及びグローバル統合プロジェクトの構想企画から実現までのプロジェクトマネジメントを担当。IBM内では、自組織の「学習する組織」化推進の重要性を訴え、「Learning Organization Initiative」を創設。コンサルタントの日々の研鑽機会の企画運営に加え、学習を阻害する根源的な要因に踏み込んで取り組むとともに、若手中堅のリーダーシップ開発を担当している。キャリアをスタートした時点で既に自社(当時のIBMビジネスコンサルティングサービス)がテレワーク化していた「ネイティブ・テレワーカー」の立場から今回の執筆を担当。
自分の机を持ったことが無い「ネイティブ・テレワーカー」
日本IBM(以降、IBM)がテレワークの取り組みを始めて、20年以上が経過しました。継続的な取り組みの結果、社会人になった時点で既にテレワークが前提で、就職して以来、会社に自分の机を持ったことがないという「ネイティブ・テレワーカー」が、既にIBMの主力です。IBMでは、テレワークが自然に存在する「文化」として定着しています。
ワークロケーションが柔軟になることの良さは、多数挙げられます。生産性向上、渋滞や満員電車の解消、保育や介護の負荷の緩和、QOL(生活の質)の向上など、個人にとっても会社にとっても社会にとっても「三方良し」の、真剣に取り組む価値あるテーマであることは間違いないでしょう。しかし、これを可能にするためには様々なハードルを越えていく必要があります。
モバイル端末の配布やフリーアドレスなどのハード面、または資料の電子化やワークフローなどのソフト面、そして、それを活用するための制度面、更には実際にテレワークが根付くことができる文化面など、テレワークの定着のためには総合的な取り組みが必要です。その過程は一筋縄ではなく、IBMでも様々な問題にぶつかりながら、試行錯誤してきた歴史があります。
この試行錯誤の過程が参考になればと考え、IBMのテレワークについて3回に渡ってご紹介いたします。第1回である今回と第2回は、「ネイティブ・テレワーカーズ・クロニクル」と題し、これまでの歩みを振り返りながら、どのような壁にぶつかり、それをどう乗り越えてきたのか、そしてそこから何を学んだのかについてお伝えします。
ネイティブ・テレワーカーズ・クロニクル
先ほど、「IBMのテレワークの取り組みは20年以上」と述べたものの、実は、最初にテレワークを始めたのは更に10年遡って30年前のこと。当時の「ホームターミナル制度」は、自宅に専用の端末を設置して、その端末にログインして仕事をするというスタイルでした。これを皮切りに少しずつ対象部門を広げていきましたが、本格的な広がりを見せることはなく、「試行」的な位置づけに留まり続けてしまったのです。
「ホームターミナル制度」が定着しなかった理由は、技術と業務プロセスにありました。技術的には、通信環境が不十分なため、作業効率が上がらなかったこと。業務プロセスについては、一部のプロセスを自宅から行うことはできても、その他のプロセスはオフィスにいなければできなかったという点が挙げられます。IBMはテレワークのためには個別のツールだけではなく、業務プロセス全体を鑑みて総合的に取り組まなければならないと学ぶことになったのです。
その後はしばらく停滞が続きますが、潮目が変わったのは2000年に近づいた頃でした。この頃から、個人へのPCとPHSの配布、グループウェアの発展など、技術的な下支えを元に、テレワークが再び活性化してきます。育児や介護への関心が高まったことも「文化」の側面として寄与しました。ワークスペースも、事業所か自宅かの2択ではなく、渋谷や品川などの中核駅付近に小規模のサテライトオフィスが設けられ、どこでも仕事ができるようになってきました。
技術が追いついてきたこの頃、課題として挙がったのが「管理」です。勤怠管理や評価、ちょっとした意思疎通など、同じロケーションであればほとんど意識しないことを、新たな手法で管理する必要性が生じたのです。これに対応するために、メール、データベース、チャットなどのコミュニケーションツールの充実と、勤怠管理など、申請系ワークフローの整備が進みました。ただし、当初は慎重過ぎた面がありました。テレワークを許可する部署を限定したり、テレワークの理由を人事部で審査の上で許可する、などのハードルがあったため、社員全体に普及することはありませんでした。
しかし、実践の中で活用の有用性と、リスク管理の緩急のポイントが見えてきました。確実に実施する必要があるのは、セキュリティーです。そのため、暗号化やデータ所持ルール、持ち歩きルールなど、様々な整備を行いました。一方で、人事への申請や目的の制限など、障壁となっていた各種制約を次々と撤廃。使い勝手が良くなっていくことに比例して活用の裾野は一気に広がり、ついにテレワークが定着したのです。
現在、IBMのテレワークは決して特別なことではなく、多くの社員が日常的に、自分のニーズにあった形で活用しています。特にネイティブ・テレワーカーにとって、自分がパフォーマンスを上げるためのスタイルが「テレワーク」であるということを意識することもありません。
定着のカギは社員観だった?
振り返ってみると、2000年前後にテレワークが再び活性化した理由は、当時の時代背景や技術の進化、制度の整備などが考えられます。しかし、本当に「活用される」までに至った最大のきっかけは、活用の制約を撤廃したことでした。では、制約を撤廃できたのはなぜでしょうか。その背景には、社員を管理しなければパフォーマンスが上がらない「ワーカー」と捉えるか、それとも、制約を無くし裁量を増やすことで更に活躍してくれれる「プロフェッショナル」と捉えるかの認識の違いがあります。
では、社員を「プロフェッショナル」として扱うためにはどうすればいいのか、また、プロフェッショナル意識を元に活躍してもらえる様になるためには、どうすればいいのか。実はこれについても、テレワークを含むワークスタイル変革がカギを握っています。
IBMには、もう一つのテレワークの流れが存在します。IBMが2002年に「PwCコンサルティング」を統合して設立された、IBMビジネスコンサルティングサービスにおけるテレワークの取り組みです。こちらは1994年に改革に着手し、2001年までのわずか7年間でワークスタイルを大きく変革した短期集中型でした。また、「制度」を変えるよりも「ワークインフラ」を一気に変えてしまうことで、半ば強制的に社員全員のワークスタイルが変革され、そのスタイルに沿った「制度」が追いかけてくるという、「インフラ駆動型」のアプローチも独特です。
そして何よりも、ワークスタイル変革を、福利厚生やワーク・ライフ・バランスの文脈以上に、「未来企業の実験室」「学習する組織」など、成長戦略の中心に位置づけて推進したのです。プロフェッショナル組織を実現するためのワークスタイル改革の事例として、次回はこの、IBMビジネスコンサルティングサービスでのテレワークの歴史をご紹介していきます。
photo:Getty Images
第2回はこちら
第3回はこちら