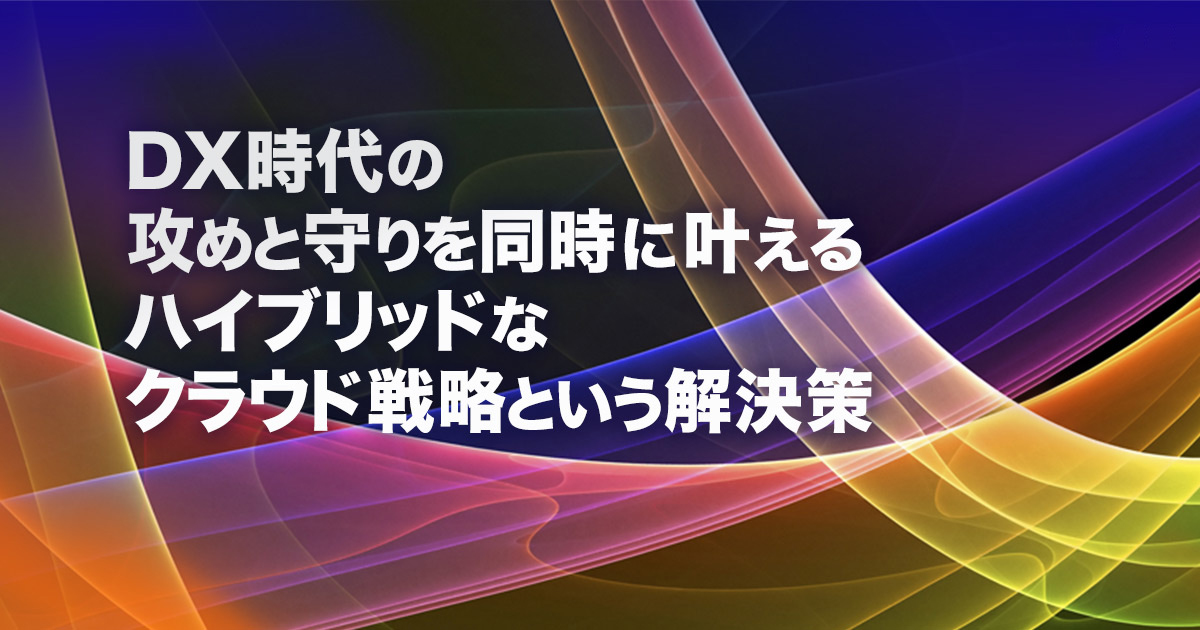デジタル・トランスフォーメーション(DX)は、いまやどの企業でも関わる課題だ。しかし、DX実現に向けて、うまく動けていない企業も多い。花王グループもそうだった。しかし、同社はDXに向けて体制整備を行い、DXに動き出した。花王 代表取締役 専務執行役員 長谷部佳宏氏がこれまでDXで歩んだ道のりを具体的に解説する。
花王グループは、先陣を切ってDXを推進する「ファーストペンギン」として、
先端技術戦略室を組織した
ファーストペンギンとしてDXを推進
いま日本の社会と企業は、大きな課題に直面している。経済産業省が警鐘を鳴らしたレポート「DXレポート〜ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開〜」では、デジタル変革の遅れにより2025年以降、毎年12兆円もの経済損失が生じるという。さらに追い打ちをかけるように、2025年には国民の1/3が高齢者になり、43万人のIT人材の不足する計算だ。これからの日本は、人材を育成しながら、デジタル改革を進めて行かなければ、本当に世界から取り残される重大な局面を迎えているのだ。
そのような状況の中開催された「Think Summit」の基調講演に登壇した日本アイ・ビー・エム 代表取締役社長 山口明夫氏は、「企業のデジタル変革は2019年から“第2章”に突入しました。クラウドやAIを顧客接点に近い部門や業務に適用する段階から、実証実験で終わっていた技術を大きく本格展開し、全社規模でビジネスを再構築する段階に入りました」と語った。
ここで、実際にデジタル変革を推進している花王グループの事例について紹介しよう。同グループは、3年前に社内に先端技術戦略室(以下、SIT)を発足させ、DXを強力に推進することを決意した。
花王 代表取締役 専務執行役員を務める長谷部佳宏氏は、「その当時、会社をDXで変革しようとしても、社内には誰も牽引するような人がいませんでした。どんどん他社がDXを進めているのに、自分たちは尻込みしている状態。そこで最初に海に飛び込むペンギン、ファーストペンギンとして、SITを組織したのです」と振り返る。
花王 代表取締役 専務執行役員 長谷部佳宏氏
同社では蓄積されたデータを活用するためにDXの実現は不可欠だった。DXを推進するにあたり、まずSITはITシステムの方向性を検討して戦略を練った。ここで、「現システムから新システムへの完全移行か部分移行か」「事業の機能を向上するのか」「消滅まで想定するのか」といった考え方を取捨選択していく必要があった。そしてSITが選んだのは、現在所有するリソースを最大限に活用しながら、新規事業を広げていく「完全拡張移行」であった。
現業を止めないシステム移行
次にSITは、DX導入のアプローチについても検討した。いきなりITシステムを大きく変えてしまうと、現業が止まってしまう。ではどうすればよいのか。
システム移行には「サブマリン方式」を採用したという。
「サブマリン方式は、ほとんどの人に見えない形で新システムを作っていく方法です。現行システムからデータを抜き出し、データの活用を検証した上で、徐々に既存システムを変えていくことで、いつの間にか出来上がっているようなイメージです」(長谷部氏)
こうして社内のITユーザーに見えないようにDXに着手し始めた花王だが、同社はさまざまな問題を抱えていた。
「効率化」ではなく「能率化」
問題の1つは、「意識改革」「スピード感」「人材活用」意識の欠如だった。デジタル化やAI(人工知能)の活用の遅れが指摘されている日本企業だが、花王も例外ではなかった。新設されたSITでは、これらの課題に対し、それぞれ大きな3つの基本方針を固めた。
日本企業のIT・AI活用に関する3つの課題に対して、花王のSITは上記のような基本方針を固めた
「まず意識改革面では、先端技術を部門主体で活用してもらえるように工夫しました。ITを活用するのは、我々ではなく、現場の全社員です。そこでSITはシステムを先導しますが、デザインをするだけで、主体となるのは活用する部門そのものです」(長谷部氏)
またスピード感について同氏は、「直列型で1つ終わってから次に進むのではなく、プロジェクトを並列型にして一気にβ版でモノづくりを進めました。そして人材活用面では、兼務を推奨したのです。何か新しいことを始めると、そこに人を集めたがりますが、我々は専門部隊のほかに、多くの部門から自由に参加してもらえるようにしました。これを可能にするために、SITは組織的に全部門にまたがる中心設計とし、コーポレート機能系列に入れました」と語る。
SITは具体的にターゲットとなる自社の領域を「R&D」「セールス」「ビジネス」「CI(コーポレート・アイデンティティ)」「人材」「ファイナンス」「SCM(サプライチェーン・マネジメント)」「ロジスティクス」「マネジメント」という9つに決めた。そしてDXで一体何が実現できるのか、そのゴールをイメージできるようにビデオをつくり、経営層に訴求した。
たとえば、このビデオではデータとAIを活用したゴールイメージとして、花王製品のグローバルなセールス市場と成長比率を国別にリアルタイムに予測したり、SNSのデータから顧客の声を分析し、花王のポジティブなイメージを数値でとらえたり、花王の顧客のトレンドを競合他社と比べるなど、ダッシュボードで展開される具体的なイメージを見せたのだ。
データとAIによって実現できる具体的なイメージをビデオとして制作し、上層部に訴求したところ、すぐにゴーサインが出た
花王グループには、社内に膨大なデータの蓄積があった。しかし、それらは残念ながらサイロ化されており、必要な時に必要なデータをすぐに取り出せる状況でなかった。データドリブンをベースに、迅速かつ思い切った経営判断を下したいと考えていた経営層にとって、このビデオは効果的だった。
「まず、上層部から理解を深めてもらうことが先決でした。全体を動かしていくために重要だからです。次に贅肉となる業務、ルーチンワークを解決しようと考えました。これが解決できると、人がワクワクしたり、社会に対して価値を見出せるようになります」(長谷部氏)
長谷部氏は「我々は1年前まで効率化という言葉を使っていました。しかし、それが間違いだと気づきました。本当にやりたいことは能率化でした。効率とは労力やコストあたりの成果の割合です。しかし、それでは従業員の心が躍りません。能率は一定時間あたりの成果の割合で、自動車から飛行機に乗り換えるようにアップグレードすることです」と強調する。
従来の業務プロセスには生産性が低いむだな部分があり、ITや機械化で自動化できるルーチンワークも多かった。SITでは従業員が楽しく取り組める仕事や、社会に価値を生み出せる仕事を主軸に置き、これらを先導できるシステムづくりを目指した。これにより、非効率的な活動を減らし、創造的な活動を増やせるようになると考えたのだ。
そこで、同社はシステムをアップグレードして、人と会社を根本的に変えていくために、IBMとの協創の道を選んだという。
データレイク構想と統合検索システムは何がスゴいのか
花王では多くのデータがシステムに蓄積されていたが、それらは散在していた。そのため、必要なときに必要なデータが、「見つからない」「つながらない」「取り出せない」という事態に陥っていた。そこで、これらのシステムをインテグレートし、データをすべて迅速に使えるように「データレイク構想」を立ち上げた。
散在していたシステムのデータをデータレイクに集約。統合検索システムから必要なデータをタイムリーにピックアップできるようになった
「すべてのデータにタグをつけ、使える形でデータレイクに入れて、必要なデータをタイムリーにWatson Explorerでピックアップできるようにしました。これにより、作業時間が短縮されるだけでなく、今まで知りえなかったことまで発見できるようになったのです。これは効率化でなく、間違いなく能率化であり、アップグレードです」(長谷部氏)
実際に研究開発部門では、データレイクから情報を統合した検索システムを使うことで、画期的な発明が生まれた。皮膚トラブルを解決するために開発した人工皮膚Fine Fiberだ。これは皮膚にサブミクロンの極微な繊維を吹きかけ、積層薄膜皮を作るものだ。長年の課題であった化粧品製剤の肌表面での持続性や均一性に飛躍的な進歩をもたらす発明だ。
統合検索システムの情報から、画期的な人工皮膚「Fine Fiber」を発明。皮膚上に極微な繊維を吹きかけ、積層薄膜皮を作ることで、化粧品製剤に飛躍的な進歩をもたらすという
「我々は、必要でない人にはモノを届けないという考えがDXだと思っています。エビデンスベースで、効果が出たかという事例を学習し、変化を予測し、誰にニーズがあるのかを、スピィーディにグローバルに展開することで、さらにアップグレードしていけると考えています」(長谷部)
長谷部氏は「新しいものを創造するとき、デジタルの力は大きな武器になります。スティーブ・ジョブズ氏の『Stay hungry, stay foolish.』という言葉は、我々にとっての強いメッセージです。ITを使って、次のアップデートされた未来を築くために、ロジカルな技術をハングリーに取り込まねばならないときが来ているのです。そのために我々の意識改革も必要です。引き続き、花王はDXを推進し、できるだけ皆様に早く新製品をお届けしたいと考えています」と語った。
スピード感溢れるDXを実現するためにIBMと共創する:IBM Garageのご紹介
当記事は、Web「ビジネス+IT」に掲載されたものです。